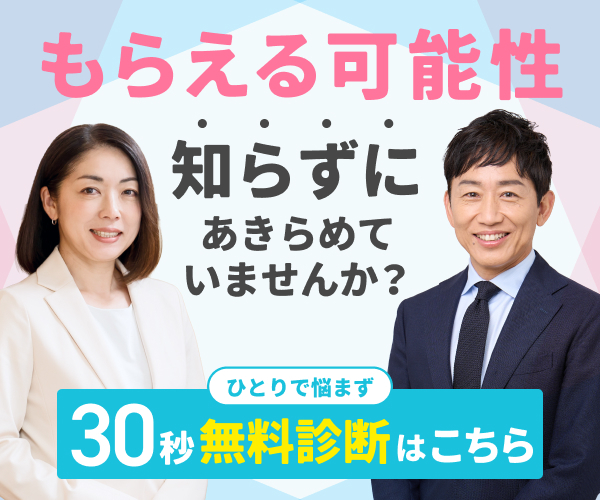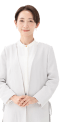ご依頼の経緯
U様(50代・女性)は、子どもの頃から集中力が続かない、不注意が多い、落ち着きがないといった傾向がありましたが、特に診断を受けることなく社会人として働き始めました。しかし、就労先での人間関係や業務の継続が難しく、職場に定着することができず、転職回数は20回以上にのぼっていました。
不眠・頭痛・息苦しさといった身体症状も現れるようになり、50歳を過ぎてからようやく心療内科を受診。そこで初めてADHDと診断を受けました。診断を受けたことで自分の状態に納得できた一方で、「この先はどうしたらよいのか」という不安も抱えていらっしゃいました。
障害年金の存在を知ったものの、制度が複雑で、自分ひとりで進めるのは到底無理だと感じていたU様。精神疾患を専門とする当事務所のホームページを見て、お問い合わせいただきました。
担当社労士のコメント
U様からご相談をいただいたのは、初診からまだ1年6か月が経過する前のタイミングでした。そのため、まずは障害年金の制度や申請(請求)の流れについて丁寧にご説明し、障害認定日(=初診日から1年6か月経過した日)を見据えて、診断書の依頼や申立書作成の準備を計画的に進める方針としました。
ADHDの特性上、U様ご自身も「計画的に物事を進めるのが苦手」とおっしゃっており、メールの確認もままならないとのことだったため、当事務所では電話を中心としたやり取りに切り替えました。確認事項はなるべく細かく分け、負担を感じさせないよう、無理のないペースでサポートを行いました。
また、U様は現在、お母さまと同居されています。ご本人だけでなく、同居するご家族の視点からも日常生活の状況を把握することが重要だと考え、お母さまにもヒアリングを実施。食事・掃除・買い物・服薬管理・時間管理・対人関係など、生活のあらゆる面で支障が出ている様子が具体的に浮かび上がりました。
これらの内容を報告書としてまとめ、主治医が診断書を作成する際の参考にしていただきました。また、病歴・就労状況等申立書においては、生育歴から現在までの困難を丁寧に記述。特に、幼少期から一貫して同様の傾向があったこと、そして社会に出てからも職場に定着できず、繰り返し転職をしてきた経緯を詳細に記しました。
その結果、障害基礎年金2級(年額約83万円)の認定を受けることができました。
発達障害の方は、自分の困難さを言語化するのが難しいことも多く、申立書などの書類作成にも大きなストレスを感じやすい傾向にあります。、そのようなときは、社労士などの専門家に頼ることをぜひ検討してみてください。
お客様からのメッセージ
「制度がとても複雑で、何から手をつけていいか全くわかりませんでした。まさか申立書に『生まれたときから現在まで』のことを書くなんて、自分ひとりでは到底できなかったと思います。
メールのやりとりも苦手なので、電話で丁寧に話を聞いていただけたのがとてもありがたかったです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。