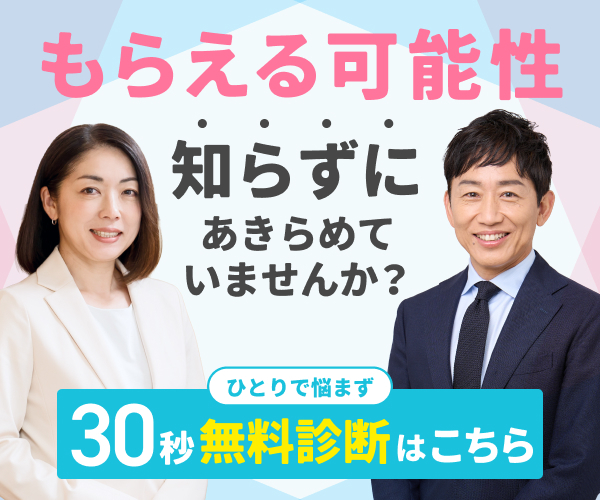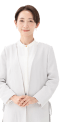ご依頼の経緯
N様(20代・女性)は発達障害(ASD)を抱えながら、東京都内のA型作業所に通い、就労支援を受けながら日々の生活を送られていました。周囲の支援者から障害年金の受給を勧められたものの、以前に相談した社労士事務所からは「A型事業所で働いている場合は受給は難しい」と言われ、門前払いのような対応を受けたそうです。
それでも「日常生活には支障があるし、就労しているといっても支援がなければ難しい」という思いがあり、他に相談できる専門家を探していたところ、当事務所のウェブサイトを見つけてご連絡をいただきました。 初回のご相談時点では、ご本人も「自分は年金がもらえる状態なのかよくわからない」と不安を感じておられましたが、「一度詳しく話を聞かせてください」とお伝えし、やりとりを重ねながら状況を丁寧に把握していくことにしました。
担当社労士のコメント
障害年金の申請(請求)において、「A型事業所に通っている=働けているから受給は難しい」と一括りにされてしまうケースは、実は少なくありません。しかし、実態としてどのような支援を受けながら就労しているのか、日常生活にどの程度の支障があるのかを丁寧に確認し、客観的な資料としてまとめていくことで、適正な審査を促すことは可能です。
N様の場合も、前に相談された社労士事務所では「A型に通っているから無理」との一点張りで、就労実態や生活の困難さには目を向けてもらえなかったとのことでした。そこで当事務所では、まず就労状況や支援の内容について詳しくヒアリングを行いました。
A型事業所での業務内容、作業時間、職員からどのようなサポートを受けているか。加えて、日常生活でご本人がどのような困難を感じているのかも、時間をかけて丁寧に確認しました。発達障害のある方の場合、自分の困難を言語化するのが難しいことも多いため、何気ない会話の中からヒントを拾いながら、本当の「困りごと」を抽出することに注力しました。
ヒアリングの手段としては、まずメールでやりとりを行い、内容が曖昧だったり、こちらの意図が十分に伝わっていないと感じた場合には、すぐに電話でフォロー。文章では拾いきれないニュアンスを言葉のトーンや間の取り方から読み取り、N様の状況を正確に把握するよう努めました。
そのうえで、医師の診断書作成時には「どのような点を強調して記載してもらうべきか」を整理し、N様に分かりやすくお伝えしました。また、日常生活における支障についての病歴・就労状況等申立書も、具体的なエピソードを交えて記載し、形式的な表現にとどまらない、実態に即した内容となるよう工夫しました。
結果として、障害基礎年金2級の受給が認められ、N様は経済的にも精神的にも安定を得ることができました。形式的な判断だけでなく、「生活の実情に即した支援」を行うことの重要性をあらためて感じた事例となりました。
お客様からのメッセージ
「別の社労士事務所で断られてしまい、自分で手続きをするにもどうしてよいかわからず、本当に困っていました。みのり社労士事務所さんでは、話を丁寧に聞いてくださって、『一緒に進めていきましょう』と言ってもらえたときは、本当にほっとしました。あきらめずに相談して本当に良かったです。同じように悩んでいる方にも、ぜひこちらをおすすめしたいです。」
※プライバシー保護のため、一部内容を変更・加工して掲載しています。